-

大雪山縦走3泊4日(赤岳~トムラウシ山)登山ガイド
2023/06/21
大雪山「赤岳~トムラウシ山」を3泊4日で縦走するプランをご紹介します。 北海道三大縦走路のなかで、最も人気があるのが大雪山縦走です。変化に富んだ自然環境をうかがい知り、スケールの大きさを体感できます。 ...
-

大雪山系「ヒサゴ沼避難小屋」宿泊とテント泊のための徹底ガイド
2023/06/14
ヒサゴ沼避難小屋(キャンプ指定地)は、大雪山の最深部にある避難小屋です。 大雪山縦走の代表的なコース「旭岳~トムラウシ山2泊3日」では、1泊目は白雲岳避難小屋、2泊目はヒサゴ沼避難小屋に ...
-
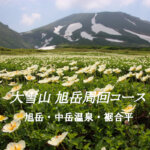
旭岳~間宮岳~中岳温泉~裾合平~姿見駅 周回コース登山ガイド
2023/06/02
大雪山の変化に富んだ自然を満喫できる日帰り周回コースです。地球創生をほうふつとさせる荒涼とした大地を歩き、温泉で火山活動の恩恵を楽しみ、見渡す限りの高山植物の花畑をめぐります。 &nbs ...
-

買ってよかった浄水器【グレイル】ジオプレスピュリファイヤーで飲む雪渓の水は極旨
2023/05/19
家族で大雪山を3泊4日で縦走したとき、非常に役立った浄水器をご紹介します。これで飲んだ雪渓の融水は思わずうなる美味しさでした。 エキノコックス症のリスクがあるから生水は飲め ...
-

登山の飲料水確保に浄水器SAWYER MINIを購入。水分補給が短時間で可能に
2021/08/29
登山の飲料水確保に、浄水器SAWYER MINI(ソーヤーミニ)SP128を購入しました。 これまで、行動中に飲料水を確保するときは煮沸消毒をしてきましたが、時間がかかるうえ、今年は山も猛暑で温かい飲 ...
-

風穴の恵みが生き物たちを支える「東ヌプカウシヌプリ」登山ガイド
2021/06/13
大雪山国立公園の南に位置する東ヌプカウシヌプリは、標高1,252mの山。ガレ場には多くの風穴が存在し、ナキウサギやエゾイソツツジなど、本来は高山にしかいない動植物を支えています。 十勝平野の大パノラマ ...
-

安全な飲み水はこう作る!北海道で登山するなら知っておくべき水場事情
2021/06/05
北海道の山には整備された水場はありません。本州のような営業小屋もないので、飲み水を買うこともできません。 登山中に飲料水を確保する唯一の方法は「自分で作る」こと。雪渓の融水や沢の水をくんで、煮沸または ...
-

【北海道の山】十勝岳~美瑛岳 日帰り縦走コース登山ガイド
2021/05/23
火山がつくりだす景観と登山の醍醐味である稜線歩きを味わう、十勝連峰「十勝岳~美瑛岳」日帰り縦走コースの紹介です。 レキと噴煙で無機質な印象の十勝岳、豊富な高山植物に彩られた美瑛岳。このコ ...
-

年に数週間しか通れない幻のルート「三笠新道~緑岳」登山ガイド
2021/03/13
三笠新道は、大雪山の高原温泉沼と高根ヶ原を結ぶ雪の回廊です。 通行できるのは、林道が開通して入山可能になってからヒグマが居つくまでのわずか数週間。幻の登山道とも呼ばれています。 豪雪地帯の大雪山のなか ...
-

【北海道の山】桂月岳登山ガイド
2020/08/14
黒岳石室の裏に位置する桂月岳。 標高は1938mありますが、石室からは標高差約50mの「小高い丘」です。 ちょっとした散策気分で登ることができるので、黒岳から足を伸ばして石 ...
-

【北海道の山】大雪山お鉢平めぐり登山ガイド
2020/08/08
お鉢平は、大雪山の中央部に位置する約3万年前の噴火により生じた長径2.2kmのカルデラです。 黒岳石室を起点に、お鉢平の縁をぐるっと1周するお鉢平めぐり(左回りコース)を紹介します。 今なお有毒ガスを ...
-

【北海道の山】藻琴山「スカイライン遊歩道」登山ガイド
2020/07/30
北海道・阿寒摩周国立公園の北端に位置する藻琴山。 日本最大のカルデラ湖「屈斜路湖」を眼下に、かなたに知床連峰をパノラマビューで楽しめるのが藻琴山の最大の魅力です。標高わずか1000mで、これほどの絶景 ...
-

エゾ鹿とぶつからないために「知っておくこと」
2019/11/16
エゾ鹿と車の衝突事故は、北海道で毎年2,000件以上発生しています。車の修理費は平均で48.2万円。 登山の移動時間は、エゾ鹿の出没が集中する時間帯と重なります。事故を防ぐ対策をはじめ、万が一事故を起 ...
-

見分けられる?「ダケカンバ」と「白樺」の違い
2019/11/03
山に登っていると、風雪に耐えるかのように地を這うダケカンバをよく見かけます。その姿は、山岳地帯の厳しい環境を雄弁に物語っています。 ところで、ダケカンバと白樺、見分けがつきますか?両方ともカバノキ科カ ...
-

まるでガラス細工「雨氷」で山がおとぎの国に
2019/10/09
先日、山で雨氷(うひょう)を観察することができました。 雨氷は0℃以下でも凍らない雨や霧が枝などに付いて、瞬時に氷結する珍しい現象です。 幸運に感謝しつつ、みなさんにも自然が作り出す一瞬の造形美を紹介 ...